
ハナコ
ケーススタディ
ケーススタディ
意見書

ハナコ
当事者の診察・診断結果、及び本件入院に関する鑑定的意見書
三吉クリニック院長 三 吉 譲
精神保健指定医
日本精神神経学会会員
日本精神診療所協会会員
日本EMDR学会及び日本臨床催眠学会会員
第1 はじめに
1 意見書作成の方法
私は、当事者(以下、当事者)本人より、第三者としての的確な診断(病歴の有無を含む)を求められました。
そこで、私は、精神科医として、直接、本人の診察を行いました。
その際、本裁判の第一審の記録、当事者が個人情報開示で公的機関から入手した証拠類を参照し、さらに当事者のこれまでの耳鼻科診療録等も本人を通して取り寄せ、参照しました。
また、私自身の経験と力量だけでは不足と思われた一部の判断については、もっとも適切だと考える他の第三者の専門医へ本人に受診してもらい、その診断も参考にしました(甲58)。
これらの結果から、本裁判で争われる被告医療法人社団S病院及び主治医K1医師ら(以下、被告医師ら)による、平成21年2月13日から同年3月5日までに行われた医療保護入院の適否につき、私の意見を以下に記します。
本意見書の構成は以下の通りです。
2 本意見書の構成
第2において、私自身が三吉クリニックで診断した診断結果
第3において、平成21年2月13日時点での病状診断
第4において、強制入院の原因となった家族問題
第5において、本件被告らの診断方法への疑問
第6において、本件医療保護入院の適否
を論じます。
第2 三吉クリニックにおける現症診断
1 診断の経過
私は、当事者の要請により、私が院長を務める三吉クリニックにおいて、診断を行いました。
診断の時期と時間は、平成23年6月10日、7月15日、9月9日、11月2日、初回は90分、第2回~4回は120分計7時間30分です。
当クリニック広瀬隆士ケースワーカーがアシスタントとして参加しました。
2 診断内容
(1)身体所見:
身長175㎝、体重70kg、体格良好、顔色良、姿勢及び動作正常、睡眠・食事ともに良好。
自覚症状なし。
他覚所見なし。
清潔を保ち、身体的にはすべて正常範囲。
常用薬物なし。
(2)精神状態検査:
① 一般的な外見:
上下黒色系のビジネスマンスーツで、靴を含め手入れよく、シミや皺も認められない。首筋や手にアカ・ほこりは認められず、臭いもなし。清潔感のある容姿であった。これは4回の診察を通じ、一貫している。
② 顔の表情:
通常なり。控え目ではあるが、表情は自然で、プレコックス感(-)
③ 姿勢:
キチンとしながらも、適宜リラックスできる。長時間の診察や問診にも耐えられ、姿勢がだらしなくなったり、異様に緊張することもない。毎回の診察でも安定していた。
④ 動き:
落ち着かない、不自然な動きは一切ない。
質問にはゆっくり考えながら丁寧な返答をされる。
繰り返しの質問に返答内容は変わらず、いつも的確であった。
⑤ 社会的行動:
度を超したなれなれしさや、反対につっけんどんな態度が一切認められない。礼節を保った態度である。
働いた収入で自活し、社会的自立をしている。
診察費用も自費支払い。
⑥ 発語:
はっきりした明瞭な日本語で、早すぎず、遅すぎずかつ話の要点をはずさず、過剰にならずまとまりを持って的確に返答できる。
発語より、統合失調症を疑わせる思考障害は全く認められなかった。
⑦ 薬物嗜癖:
常用する薬物はアルコール(-)、タバコ(-)、鎮痛剤等の薬物(-)。
⑧ 気分:
安定している。
一貫して、うつ状態でもなく、躁状態でない。気分の動揺もない。
4回の診察にわたって不変である。
⑨ 不安:
不安状態なし。
不安に伴う動悸や、口が渇く、震えるなどの身体症状は全くなし。
⑨ 思考:
話にまとまりあり、一貫性がある。
滅裂思考(-)、思考内容に一審判決に対する集中した思考ある も、強迫的なものではない。すなわち、強迫観念(同じ考えが意志に反しくりかえし現れる)はなく、強迫行為(意志に反してくるかえし行う儀式行為)もない。
⑩ 解離性障害:
一貫して意識清明。
もうろう状態に入ることなく、解離症状なし。
⑪ 妄想:
妄想はない。事実に基づいた考えである。
妄想のわかりやすい質問として
「テレビで自分のこと言ってますか」(考想伝播)
「考えが自分の心に埋めこまれてますか」(考想吹入)
「誰かがあなたの心や考えを抜き取りますか」(考想奪取)
このような質問をするも、本人にはそのような妄想は全てなく、統合失調症を疑わせる、上記症状は全くなし。
⑫ 不当入院、不当判決について
これに関する本人の信念は妄想かについて、以下詳述する。
ア 不当に入院させられたこと;
データを検討するに真実である。
イ 不当な一審判決と考えていること;
データを検討するに真実である。
ウ どのくらい強く信じているか;
信念を持つ理由に根拠がある。強く信じる理由があり、それ を裏付けるデータがある。
エ その信念は、文化的に決まっているか;
精神科病院の強制入院は、医学的根拠を持ちかつ人権を尊重し なければしてはならない事が、日本の法律で保証されている。かつてのソ連では共産主義に反対するだけで、妄想型統合失調症とされたが、日本国憲法は、信仰・思想の自由を保障している。すなわち、不当入院・不当判決は許さないという信念は日本では文化的に決まっている。
文化的に決まった信念で、本人は裁判という行動を続けている。
⑬ 錯覚:
正常な知覚で、錯覚は全くなし。
例えば、物音→泥棒の音。物影→人影。こういった認知の歪みは全く認められない。
⑭ 幻覚:
幻聴や幻覚を全く欠いている。
外界を正確に認識し、きわめて正常である。
⑮ 見当識障害:なし。
日時、場所、自分がここにいる理由等全て的確である。
⑯ 注意力と集中力:
計4回2時間に及ぶ診察で、注意力・集中力は一切途切れない。
並外れた能力であり、一点に集中する事とそれに没頭できる特質がある。
⑰ 記憶:
過去の記憶が並外れて高い。
一時に記憶できるカメラ・アイの才能がある。
3 専門医紹介
⑰の並外れた記憶力と没頭できる注意力集中力及び海外留学やその後の勤務、一審で一人で闘い抜いた行動力、集中力より、ADHD(注意欠陥、多動性障害、過集中タイプ)傾向のアスペルガーを疑い、専門医を紹介しました。ADHA傾向をもつアスペルガーとしては、過去の人物としては、野口英世やエジソン、最近では、ビルゲイツがそうだと言われています。
専門医への紹介状と返書を本人に交付しました。
専門医の診断では、かつて、その傾向あるも、今は正常範囲とのことでした。
4 診断結果
以上より、現在診断は、社会的自立をした、心身共に健康な青年であり、精神障害者ではない、と診断しました。
第3 平成21年2月13日時点における病歴
1 問題の所在
私は、上記の通り、直接診断をし、専門医も紹介し、当事者は、精神障害者ではないと診断しました。
それでは、私の直接診断に遡る平成21年2月13日、医療保護入院の時点での状態はどうだったのか、これを次に論じます。
2 耳鼻疾患
先ず、耳鼻疾患については、当事者が持参したカルテから見て、耳鼻疾患があったことは間違いないと考えています。
3 統合失調症
では、統合失調症はどうか、検討します。
(1)江北保健総合センターの精神科医の判断
本件医療保護入院の約3ヶ月前、平成20年11月17日午前、母から相談を受けていた足立区江北保健総合センターの保健師が、精神科医を連れて、「精神科疾患の有無と診断治療の要否の判断のため」という名目で、当事者と面会しました。このときの記録が、情報開示によって取得されています(甲8、12頁)。
このとき、本人はベッドに寝ていましたが、「昨日寝るのが遅かったので、休んでいた。今何時ですか?寝起きなのでボーッとしていますけど」と穏やかに応じています。保健師が、精神科の医師と一緒にきたことを伝えると、「頭が痛かったが、手術をして、なくなった。今は大変な時期だが、また仕事をしていきたい」と当事者は答えています。
このようなやりとりの後、同行した精神科医は「抗ヒスタミン系内服中のため、やや眠そうであるが、対応は礼儀正しい。家族に対する強い攻撃性や『うらみ』は感じられる。現状についての認識はっきりしており、現実検討が障害されている印象はない。明らかな妄想は認めない」と診断しています。なお、耳鼻科のカルテに照らすと、ちょうどこの時期に、K耳鼻科からボルタレンを適正に使用中であったと思われますが「やや眠そうな」以外は特に問題点は認められていません。
すなわち、本件入院の約3か月前にあたるこの時期に、江北保健総合センターの精神科医は、当事者に思考障害や現実検討能力の障害、及び妄想のないことを確認しており、この時期、当事者が統合失調症ではないことは明らかです。
(2)Tクリニックでの診断
当事者は、本件医療保護入院の後、平成22年3月29日から同年10月8日まで、Tクリニック院長で精神科医のT医師の診察を計5回受け、「統合失調症であるという根拠は何もございません」という診断を受けています(甲15)。これは、本件入院の1年後のことです。この診察は、同センター長が当事者に勧めると同時に、母にも協力を求め、同医師は双方を診察した上で診断しています。
(3)以上の診断状況を図表にすると以下のようになります。
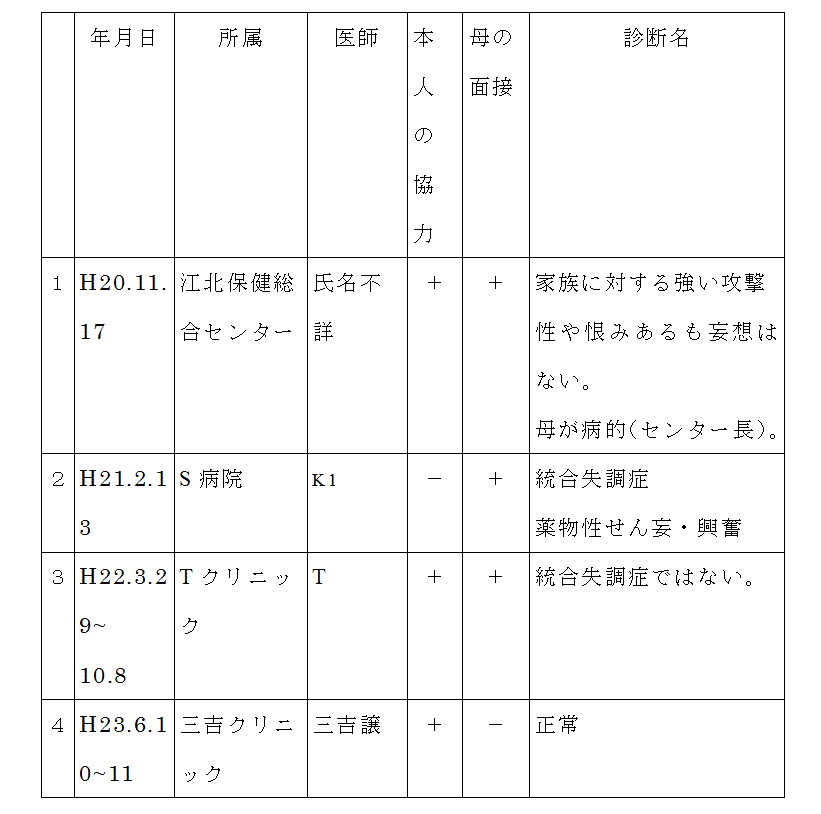
* 三吉クリニックで母の面接がなかったのは、家族機能が崩壊したため不可能であった。可能なら当然施行しました。
(4)統合失調症に関する結論
当事者は4人の精神科医の診察を受けていて、3人の医師が正常としていて1名のみ統合失調症+薬物性せん妄・興奮としています。
江北保健センター、T、三吉の3人の医師は、本人の自発的協力の下で診察を行っています。K1医師の診察は、母からの情報あるも、本人の意志に反して、本人の協力が一切ない状況で行っているに過ぎません。
精神科診察は、本人の信頼と協力があって初めて正確になされるのであり(これをラポール(疎通性)ができるという)、それがない状況での診察そのものが不可能です。すなわち、正しい診察条件を欠いていて、診察そのものが出来ない状況です。
仮に、3人の医師の診断は間違いで、K1医師の診断が正しいと仮定したばあい、統合失調症は、一度、発症すると生涯にわたるストレス脆弱性が続く病気です(甲58、P137上から8行)。従って、S病院入退院後、母・兄のトラブルの継続や、その後の自立の苦労の中でかつ服薬もしないで、再発しないことはまず考えられません。この点からもK1医師の診断は誤診であることは間違いありません。一審判決はこの点の検討を全くしていません。
4 薬物やアルコールによるせん妄などないこと
(1)問題の所在
被告医師らの診療録には、アルコールやボルタレンの過剰摂取(OD)もその原因と断定しての「せん妄想・興奮・滅裂」の症状記載があります(甲18、9頁ないし診療録9頁)から、その根拠があるかどうかを検討します。
(2)診療録
しかし、診療録には、アルコール臭の確認や血液検査・肝機能の数値等何ら実際には確認されておらず、それを実証する臨床的所見の記載も証拠もどこにもありません。
診療録の6頁「相談表」でもアルコール類の 種類、一日量、頻度の欄は空欄で、相談員に聴取された思われる母にとっても、当事者の飲酒状況すら不明であったことは明白です。
入院翌日の血液検査の結果、肝機能全くの正常値で、「慢性的な過量飲酒や過量の鎮痛剤、鎮静剤の服用」を疑わせるような根拠は全くありません。
(3)救急隊
また、医療保護入院の当日搬送をした救急隊の記録(甲14、4頁)にも、アルコール臭やOD(過量服薬)の徴候・痕跡(薬のパッケージの残りゴミの確認=過量服薬が疑われる場合にはこれを探して服薬量を確認しようとするのが通常の救急活動)等の記録は皆無です。逆に記録には意識レベルは「清明」と記され、「ベッド上に横臥位となっていた」「めまい、全身の痛みを訴える」とあるのみで、「体温は37.0℃」の微熱、救急隊の処置は、「毛布で保温」です。この記録の全体を見れば、救急活動開始から搬送に至るまでの22分間、当事者に「判断能力の耗弱・喪失」や「自傷・他害のおそれ」がなかったことも明白で、「せん妄、興奮、滅裂」や「飲酒・OD」、「不穏」などをうかがわせる記載は皆無です。
なお、同記録には、「情報源者」の母からの話として、「S病院で、息子の精神的な面からくる、めまい、全身の痛みの相談のため医師と面談した結果、とりあえず当病院を受診して欲しいとのことからの要請」 とだけ記載されているのみであり、母もアルコールやODに何ら言及していません。
(4)結論
以上より、当事者には、アルコールや薬物を理由とした精神障害 などなかったことは明らかです。
5 当日午前中の面談の検討
(1)問題提起
以上のように見てくると、医療保護入院の基となったのは、医療 保護入院に先立つ当日午前中の、母と被告医師らとの面接しかないのではないかと思われます。
そこでの様子を記録した、診療録6~7頁とそれに続くページを検討してみましょう。
なお、甲59、3頁によれば、この面接を行ったのはK2医師だとされています。
(2)検討
「相談表」では、「7、どのようなことでお困りですか?(どんな症状がありますか?)」という問いに対して「怒りっぽい、暴力をふるう」と母は回答しています。「いつ頃から?きっかけとおもわれることは?」という質問に対しては、「26才頃から、兄と自分(母自身)と関係」すると回答しています。
医師との面接では、「以前は当事者と兄は仲良かったが、当事者が母へ暴言を始めたので、兄が当事者に家を出ろと言い、関係が悪くなった」と母は答えています。当事者から母への「暴言」の中身は、朝早く洗濯機をまわすと「ウルサイ!」と言ったり、めまい、頭痛に困っているのは「母のせいだ」となるということです。母は、さらに「このためにパトカーを呼んだこともある」、「大声を出す。」、「テメーのおかげでこうなった!」と「母を責める。同じことを繰り返す」、等とあります。
医師は、これらの発言のみで、「精神症状」の欄に「母への暴言、暴力。父へも暴力」の他、「身体症状も」とだけ記載しています。しかし、「暴力」と言っても、「暴言や物を蹴る」行為なのか、あるいは体を傷つける、ケガをしたといったレベルの「暴力」なのかが大切です。この時点での母の訴え方によく注意を向ければ後者の事実は示していません。
また、「暴言」や「暴力」が何故「精神症状」とみなされたのかについては、何ら検証がありません。「暴言」も「暴力」もそれ自体だけでは、治療の対象となる「精神症状」ではありません。
むしろ、母との面接を記録した上記診療録の記載からは、当事者に自傷他害のおそれのあるような、強制入院や逮捕によって対処しなければならない緊急性のある「暴力」がなかったことが、はっきりと確認できます。
6 平成21年2月13日当時の病歴診断
以上より、医療保護入院当時の病歴について、私の結論は以下の通りです。
① 当日はカゼ気味で、臥床中、微熱があって耳鼻科通院中で鼻づまり時の症状でした。ボルタレンは頓服として使ったことがあるのみで、常用していませんでした。すなわち鎮痛剤依存症も、アルコール依存症もありませんでした。
② 母は、だましうちの入院をK1医師と共謀しました。そのため、救急車を本人は耳鼻科受診のためと勘違いして同乗しました。
③ S病院K1医師による強制的な医療保護入院に対し、本人は、怒り抗議しましたが、黙殺され、電気ショックまで受けさせられました。
④ ③の怒り・抗議は、全く正常な行動です。法治国家日本でこのようなことが許されていい筈はありません。母の自作自演という意見は事実に基づいており、妄想ではありません。本人が当時言っていたことは、正確な事実解釈です。
⑤ その後、当事者は、病院の中で、無力化された自分を認め、ひたすら忍耐し、良い患者を演じ、退院を果たしました。これは、並外れた注意力・集中力・判断力を持ってしかできないことです。現在では、北朝鮮より脱出を図り成功する人たちに見られる特質であろうと思います。この当事者は、サバイバー(生還者)といってよいでしょう。
第4 家族問題
1 結論
上記のとおり、当事者は入院当日、「精神障害」を有している者ではありませんでした。では、なぜ当事者は医療保護入院することになったのでしょうか。私は、この背景には、家庭内でトラブルがあり、トラブル解消の手段として医療保護入院が利用されてしまったのだと考えています。以下、その根拠を説明します。
2 家庭内のトラブルの背景
(1)兄の暴力に対する被害届の提出
入院に先立つ平成19年6月23日、兄から弟である当事者が「出ていけ」と暴力をふるわれる事件がありました。当事者は、この兄の暴力について、警察に被害届を提出し、その被害届は受理されました。その後、当事者は、兄から手切れ金の如く渡された資金で家を出ましたが、母は、当事者が「ストーカー行為」と表現するほど執拗に当事者を追いかけ、被害届の取り下げを迫りました。母の執拗な行為は、当事者ばかりでなく、被害届の出された警察や相談機関にも及びました。母親は、「暴力をふるうのは当事者の方だ」というアピール等、繰り返したのです。
母の真情を察すれば、当事者である弟とは違い、早くから働いて生活費を支えてくれている長男を、二男が刑事告訴するなど、これほど理不尽でいたたまれないことはなかったでしょう。当事者が被害を訴えているような、母から「自作自演されている」「いたぶる」ように見える行為が続いたことは、双方とも相手の立場が汲み取れず、コミュニケーションの困難さが遷延する中では、自然な帰結とさえ見えてくる面もあります。
(2)母親が執着している借金問題
加えて母と当事者との間には、500万円以上の金銭の貸借関係と返済滞納の事実があります(母の陳述書、乙3)。
その真偽はともかくとして、母にしてみれば、アメリカに留学し、大学まで卒業していた当事者からお金を得ることができなかったことを納得していなかったことを窺わせる事実です。それまで母から「借金」と位置付けられて毎月10万円の返済を求められ、この12か月で計120万円もの返済をしてきた留学中の学資の返済が、退職後にはできなくなりました。母からの毎月10万円の返済請求は、翌平成19年6月に兄の暴力によって家を叩きだされるまで続き、「あなたが家のお金を使い果たした」「いくら使ったか考えてみな」等、父母から働かないことをいつも咎められ、そのたびにトラブルとなっていたこととも符合します。
3 母による執拗な行動の具体的内容
母親は、当事者を、自分の思うとおりにさせようとして、並行して2か所の保健総合センターを訪問しています。
(1)竹ノ塚保健総合センターでの相談
情報開示記録によれば、母が当事者のことを竹ノ塚保健総合センター保健師に相談するようになったのは、平成19年9月12日以前からです(母の相談内容、開始日等は黒塗り)(甲12、7頁)。
同保健師は翌平成20年6月まで推定6回以上(黒塗り用紙が最低6回分あり)、母のみからの相談を受け、その後同6月17日、西新井署U刑事から、「110番が頻回にあり、その都度出勤するも、本人は冷静に対応できており、措置にならず」との「状況報告」を電話で受けています。続けて2日後の同19日には、「本人、兄とも会ったこともある」同署のS氏より、「母とは折り合いが悪いが話は通じる。鼻の手術後、お金がないので受診しておらず、調子悪そうなので受診をすすめた。措置には当てはまらない」との本人の様子が報告されています。
すなわち、母が頻回に訴えてくるものの、当事者を逮捕すべき要件も、「自傷他害のおそれ」として措置入院にしなくてはいけない要件も見られないことが、警察官と保健師との情報交換で確認されているわけです。当事者の陳述によれば、母が「自分自身が納得しないことがあるたびに110番通報する」、そういうことは、過去に別件でも繰り返されていたようです。この時期は、当事者は兄の暴力に対し被害届を出して受理されているわけですから(何の根拠もなければ受理されません)、警察の方でも兄や母から聴取した上で、判断を保留し続けているはずの時期です。母はこの被害届の取り下げを求め続けており、「当事者の方の暴力や精神病」を繰り返しアピールすべき動機があります。
(2)江北保健総合センターへの訪問
他方、当事者が足立区鹿浜にある実家へ戻ると母は足立区江北保健総合センター相談に行っています(甲8)。足立区江北保健総合センターの保健師が、竹ノ塚の場合と同様、上記の直後の同年10月17日に当事者宅を訪問します。保健師は当事者及び西新井署のS氏と話して、母が竹ノ塚のセンターへも相談を並行して繰り返していたことを初めて知ったようで(母はそれを言わなかったということ)、平成20年10月20日、そちらにも経過を聞き、また先の西新井署のS氏からも電話で「本人や母と両方会い、話した経過がある。本人の訴えもよくわかる。通常のやりとりもできる」聴取しています。
その後も母からの相談が続いたよう(黒塗り)で、同11月17日午前、「精神科疾患の有無と診断治療の要否の判断のため」として、母から本人の部屋へと通された同保健師と精神科医が訪問し、精神障害のないことを診断されたこと(甲8、12頁)は前述のとおりです。
すなわち、母が頻回に訴えてくるものの、当事者を逮捕すべき要件も、「自傷他害のおそれ」として措置入院にしなくてはいけない要件も見られないことが、ここでも、警察官と保健師との情報交換で確認されているわけです。
(3)本件医療保護入院の意味
母は上記のとおり、2か所の保健総合センターを「はしご」して訴えましたが、どちらのセンターもきちんと回を重ね、双方から丁寧に事情を確認したがために、母の願いをかなえてはくれませんでした。
そのため、母は、両センターで長く相談してきた経験を伝えな いまま、2月13日午前、突然に、S病院に当事者の医療保護入院を求めました。そうしたところ、S病院は、医療保護入院をあっという間に決めてしまいました。当事者は、まるで母の「通りすがり」のS病院で、僅か35分の間で医療保護入院を実行されたのでした。
4 本件医療保護入院直後の江北保健総合センターの判断
(1)面談時の説明
江北保健総合センターは、平成21年11月24日、当事者本人、センター長、保健師2名同席で面接しました。その日の記録(甲8、20ないし21頁)によれば、同保健師は当事者に、次のような重大な告白をしています。
「実際に被害を受けているのだから、母親の精神状態が治療できるものか否かを医療機関につなげることが必要と思う。でないと再び別の形で被害を受ける。ご本人は自我がしっかりしているからこの場で伝えるが、昨年10月以降に、前任保健師が保健所医師と言って、一緒に訪問した医師は精神科医である。その診断を開示できないが(その後情報開示)(甲8、20頁19行目)『さすが精神科医』と思うご本人の見立てをしていた。同じくこの場で伝えるが、お母さんにとって貴方を国保に加入させて精神科病院に入院させることは、2年前からの願いだった。だから今回入院させられたことは、母親にとって成就である。」。
さらに、当事者が「今まで母親にさんざん、振り回されてきた」経過を話したあと、同センターのセンター長(医師)は次のように話してこの会談を結んでいます。
「母の行動は病的であり、医療につなげた方がいいと思われる。それとは別に貴方自身も自立(親離れ)しないといけない。」。そして、後日センター長は、前記のT医師への受診を、当事者と母に勧めたわけです。
(2)江北保健総合センターの判断に対する意見
同センターは、本件入院の直前から直後に渡り、母からも当事者からも、双方向からの相談を重ねてきた上で、上記の通りの判断をしています。
この結論は、非常に的確であり、私も同感です。
5 家庭内紛争に関する私の見解
私は、上記の母の行為を断罪する意図はまったくありません。母の真情も当事者の真情も同等に最大限斟酌できるよう、努力すべきでしょう。母は診断・治療の専門家でもなければその執行者でもありません。
精神科医は誰であれ、患者と家族との間に争いがあるような場合には、本人や家族からの一方の話ばかりを偏って重視してしまうと、一方の思いや目的、家族間紛争に巻き込まれてしまうことがあります。紛争の存在を見落とさず、慎重に双方の話を適度の距離を置いて傾聴した上で、紛争と症状の所在とを適切に見分けていく注意を怠っては、適切な診断はできません。
患者を入院させようとする家族の方に、より深い病理が診られることもあれば、家族間の紛争が原因で、様々な心身の症状が本人や家族に現れている場合もあります。あるいは本人や家族の一方、または両方の症状が原因で、家族間の紛争が起きている場合もあります。
本来、精神科医が介入すべきではない家族間の紛争も多々あります。そのような場合には、他に適切な援助者や機関、手段等を探し、繋げ渡していくことも肝要なのです。
第5 被告らの診断の仕方に対する疑問
1 問題の所在
本件では、被告医師らが、当事者の診察を行う前の段階で、当事者に対して医療保護入院することを既に決めていたのではないかという疑いがあります。
以下の事実が、被告医師らが、そもそも本人に会う前に医療保護入院を決めていたのではないかという疑いを抱かせる根拠です。
2 入院に先立って「統合失調症」と決めつけていること
本件では、夕刻の入院に先だって、当日の午前中に、母のみで被告病院で医師との面接を行っています(甲18、6頁)。
そして、当事者のS病院入院期間中の同病院診療報酬明細書、医科入院外の明細書2月分(甲28、5頁)をみると、「13日中に外来受診し、夜間に救急で入院となる」とあり、日中外来受診分の「通院・在宅精神療法(30分以上)」の医療点数360点と初診料273点の計633点(6330円)が診療報酬請求されています。しかも、驚くべきことに、被告医師らは、まだ当事者本人と一度も会ったことすらないのに、この午前中の報酬請求書の診断名は「統合失調症」と記載しています。
すなわち、被告医師らは、当事者と会って、診察する以前から、当事者を統合失調症と扱おうことを既に決めていたことを意味します。本人への面会前に、医師が、患者を統合失調症と決めつけることなど、本来ならあり得ないことです。
3 母の希望と沿う形で医療保護入院が決定されていること
入院当日の午前中、母が被告病院で医師と面接していることは既にふれました。その際作られた診療録(甲18、8頁)には、「暴力。母は医療保護入院希望。あとでうらまれても良。入院治療を強く希望」と母の要望としてだけ無責任に書き連ね、それに流されたかの如く、専門医としてどういう検証をし、判断をしたのか、何も示されていません。何も記されないまま、「お迎え入院を検討」とだけ結論しています。
すなわち、前述のとおり、この母との面会だけで、統合失調症と決めつけ、「医療保護入院」の方針を決めていることになります。
4 当日の診察時刻の記録のずれ
救急隊の記録(甲14、3頁)によれば、「病院決定」が18時22分、S病院「到着」が18時33分、「医師引き継ぎ」が18時50分です。
ところが、S病院診療録(以下、診療録)によれば、救急来院時刻が18時20分(8頁)、医療保護入院の決定・隔離・拘束が必要との判断の診療録記載が18時30分(20頁)となっています。
すなわち、救急隊の方の記録の到着時刻より以前に、被告医師らによる診療録が作成されていることになります。
したがって、被告医師らであらかじめ、診療記録を作っていたのではないかという疑問が生じます。
5 診察時間の短さ、杜撰さ
のみならず、実際の被告医師の診察行為も、診察行為と呼ぶこと自体ためらいを感じるくらいとても強制的、一方的で杜撰なものです。被告医師らと当事者本人とが面会後、自身の目的とする耳鼻科受診でないことに気づいた当事者は、母にだまされたことに気づいて怒り、「オレは自作自演されている! 両親がオレをいたぶる!」と真情を吐露しかけます。被告医師らは、そのように当事者が「興奮気味にまくしたてる」と、これのみを診療録に記載した(甲18、25頁)後、唐突に、搬送してきた救急隊がそれをまったく認めていないにも関わらず、「AL(アルコール)やボルタレンなどを大量にOD(過量服用)していることによるせん妄興奮強い」と、何ら根拠、情報源、検査値等の併記のないまま即断で記載しています。そして、これ以外の所見の記載もないまま(表情、瞳孔、眼球結膜、口の渇き、プレコックス感等、被告医師らが第一審で必須診断要件として陳述していたはずの観察所見の記載も皆無)、上記18時30分、医療保護入院・隔離・拘束を決定しています。
さらに、診療録(甲18、22頁)の18時30分の記載では、「救急車にて外来に到着、Dr診察、興奮気味で診療室を出ていこうとする。スタッフ数名にて静止し、再度Drと話しをする。その後も落ち着かないため、HPD(5)(セレネース5㎎)2管とラボナールを注射し、四肢体幹、肩、拘束施行」とのみ記載しています。当事者が、本人が望んでいない医療保護入院、いわば、診療契約の押し売りに対して怒り、これを拒否して帰ろうと「診療室を出ていこうとしている」だけであるにもかかわらず、これを静止しても「落ち着かない」という理由だけで、抗精神病薬をいきなり注射し、ベッドに縛り付けてしまっています。このように被告医師らの行為は、およそ診察の体をなしていませんから、最初から医療保護入院ありきの結論を決めていたと考える外ありません。
6 母親との面談すらないこと
この疑念をさらに裏付けるのが、被告K1医師自身は、強制入院決定・拘束・注射の実行時刻である18時30分より前には、母の話すら聞いていないことです。母は、前述のとおり入院当日の午前中に、被告病院に来て、医師と面談していますが、この医師は被告医師ではありません。第1審の記録を見ると、K2医師だとされています。
すなわち、被告K1医師は、母の話も聞かず、かといって当事者の診察もきちんと行おうともしていなかったわけです。それなのに、医療保護入院を即座に決めたのは、あらかじめ、医療保護入院を行うことを決めていたからでしょう。そして、前記18時30分より後になって、母と初対面して聴取した記録が診療録にあることが明らかです。
7 入院後の対応、診断の揺れ
上記のとおり、当事者自身はろくに話も聞かれないまま、すでに「医療保護入院」の方針が前提にされてしまった後で、それと知らずに搬送され、わずか10分間足らずの拒否の言動中に注射・拘束・強制入院を決定され、その後の通電、監禁、服薬等、重大な心身への侵襲を被りました。
その後の入院期間中の診療録にも看護記録(甲18)にも、上記のずさんな診断・入院のプロセスが再検証された形跡はなく、当事者の抗議の言動はすべて「不穏」「興奮」「被害妄想」等の「症状」として記載され続けたままです。
これに対して、当事者は、途中から、抗議をしていては病気だと決めつけられ退院できないと賢明に判断し、意識的に、抗議の言動を止めることにしました。そして、その結果、被告医師らは、当事者を医療保護入院させ続けていくことは無理であると診断せざるを得なくなりました。このようにして、本人の意識的な努力により、「任意入院」への切り替えを果たし、被告医師らは上記「症状」が「軽快」したとの理由をつけて、退院に至りました。
当事者退院後に母のみと面会した際に記入されたと思われる診療録(甲18、8頁)に至ってようやく、「Al(アルコール)やクスリをOD(過量摂取)している様子はない。Pat(当事者)と母のまさつ多い。Patを放ったらかしにできるかどうかがポイントであろう」と書かれています。この内容を、この時点で、K1医師はようやく母に伝えました。
そして、「退院証明書」の「入院に係わる傷病名」も「不安障害」に変更されています(甲18、58頁)。
これは、当初からの診断・治療・処方に対して、誤診ではないかという疑問が湧いた結果かも知れません。
第6 本件医療保護入院の適否、当否
1 医療保護入院をさせるべきではなかったこと
精神保健福祉法は、患者への隔離拘束を伴う医療保護入院を執行できる専門医として、精神保健指定医を規定し、治療の名のもとで患者の人権への恣意的な侵害が発生しないよう、適正な手続きを定めています。本件では、それにもかかわらず、患者への逮捕・監禁・拘束行為、薬剤・通電等、身体への重大な侵襲を伴う医療保護入院が、上記のとおり、適正な診察過程、診断根拠の明示・治療方法の本人への説明・同意等のないまま、これに先立っていきなり一方的に強行されています。
医療保護入院は、「精神症状により、判断能力を耗弱・喪失した患者」であったり、「自傷他害(のおそれ)を伴う場合」に行われる措置入院とは異なります。当事者からの同意を得る努力を一切することなく、強行した本件医療保護入院の違法は明らかです。
また、被告医師らは、当事者の発言を暴力や暴言、被害妄想と決めつけました。しかし、被告医師らは母の話の検証を怠ったまま、丸ごと真に受けました。そこには、被告医師らの専門医、指定医としての技量・注意義務・倫理のかけらも感じられません。誤診をし、当事者を同意なく拘束し、通電まで行った、被告医師らの行為は、許されるものではありません。
初対面時に、当事者からの異議申し立てを尊重し、何故それほど怒ってただちに帰ろうとするのか、その言い分をきちんと教えてほしいと、最低限の市民社会の常識的な礼儀を尽くし、突然の診療契約の押し売りの無礼を詫びた上できちんと尋ね、その怒りにこそ耳を傾け、それでも当事者が帰るのであれば、後日その言い分を聞かせてほしいとでも伝えて見送っていたならば、こんなことにはならなかったでしょう。これは、指定医・精神医療従事者としてのイロハのイです。先に母親から相談された地域の保健師らは皆、そのように適切に対応しています。
しかし被告医師らは、有無を言わさずいきなり注射、拘束し、全身麻酔をかけ、強制的に電流を通電する行為にまで一気に及んだというのが本件の実態です。
さらに、本来、母親との間で紛争があるのですから、当事者の医療保護入院の保護義務者に母親を選ぶのは不適切でした。母と当事者との間には、母親の主張によれば、500万円以上の金銭の貸借関係と返済滞納の事実があります)。仮に、百歩譲って、上記一連の出来事で、母に何ら悪意はなく、むしろ当事者を思う善意を動機としていたのだとしても、結果として、両者は利害対立関係に至っていたことは明らかです。
2 医療機関が取るべきであった対応
当事者は、家庭内トラブルの渦中にあった正常な青年です。
青年としては、最終発達段階で、社会的自立途上にあり、本人並びに母・兄への援助は必要でした。
しかし、援助の仕方を被告らは間違ってしまいました。
このような青年・家族に対しては、青年を医療保護入院させてしまうだけという対応を取ったために、基本的人権無視の法律違反がありという以上に、この家族の決定的な崩壊・離散を招いてしまいました。
平成21年2月13日に、被告医師、医療機関が行うべきであったことは、家族全員に対する家族カウンセリングであり、竹ノ塚保健総合センターや江北保健総合センターの取組の継続でした。このやり方で、しばし辛抱していれば、家族の再生がなされたと考えられるにもかかわらず、被告らの行為によってそれが不可能となってしまいました。
以上
ケーススタディ